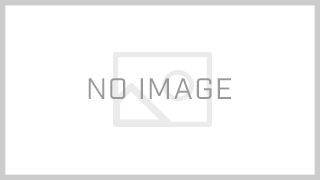内省する際には「なぜ」を考えがちだが、なぜを考えても、もっともらしい理由を思いつくだけで自己認識には役に立たない
「なぜ」は自己像の反映
「なぜ」は実際の自分を映し出さない
自分が信じている自分を投影するだけになる。
簡単な例だと
商品を買ったときに、買った理由を「よい商品だと思ったから」「お買い得だったから」
ともっともらしい答えを言うことが多いが
実際のところ、店側の策略によって買わされていることが多い。
なぜ相手のことが嫌いなのかを「なぜ」で考える時
この前、「約束をすっぽかしたから」ともっともらしい理由を作り出すが
実際は、それ以前から嫌いだし、約束をすっぽかしたことなんてすぐに忘れていたレベルの話を掘り返しただけということがある。
「なぜ」は1つの結論に帰結しがち
「なぜ」を問うと、1つの絶対的な真実があると考えて探求を始めてしまいます。
ですが、私達は複雑でそんな絶対的なものはないし、「なぜ」の答えがでた瞬間に終了し、別の視点から見ることができなくなってしまうからです。
「なぜ」は間違った自分を絶対的なものとして定義してしまうという問題があります。
「なぜ」は悪い方向にいきがち
内省に「なぜ」をあまり使わない理由の1つは、マイナス感情にいきつきやすいという点
なぜは過去の自分が今の自分に大きな影響を与えているという視点にたっています。
なので、自然と過去の被害者という立ち位置になります。
何を使う
「なぜ」を使ってはいけないなら、なにを使えばいいのか?
その答えは「何」を使うです。
「何が、そう考えさせる?」
「何によって、私は商品を買ったのか?」
「この美術品の何が自分を感動させたのか?」
これらの質問は、自分に絶対的なものを持つことがなく。複雑な自分を理解するのに協力してくれます。
自分への新たな情報を仕入れること、これが自己理解です。
過去の自分と今の自分を無理やり一本線で繋ごうとする行為は自己理解ではありません。
内省以外には「なぜ」は役に立つ
内省において、なぜは間違った答えにいきつきやすいです。
ですが、内省以外のことに関しては「なぜ」はしっかり役に立つので勘違いしないようにしましょう。
「なぜ、この商品は売れないのか?」
「なぜ、彼はそういう発言をしたのか?」
「なぜ、この会社は傾いているのか?」
このような問いには客観的な視点で取り組むことができ、ではどうすればいい?という未来への問いへ移行しやすいからです。
この場合はの「なぜ」は反省を促し、次の行動へ繋げやすい問いになります。
「なにが。この商品を売れなくしているのか?」
「なにが、彼にそういう発言をさせたのか?」
と言い換えてもいいですけどね。
「なぜ」の弊害は少ないです。